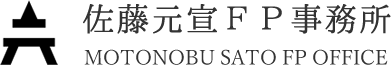本ページでは、所得税の配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための条件を紹介しています。
また、当事務所のFP相談事例から配偶者控除や配偶者特別控除を受ける際の注意点や節税対策も紹介していきます。
なお、本ページは、2016年11月20日に初めて公開したものを大幅に加筆・修正・追記を行い、令和4年度の税法に基づいた内容となっています。
そのため、令和4年度の年末調整や確定申告で活用できる内容です。
目次
【簡単におさらい】所得税の配偶者控除について
所得税の配偶者控除について、すでに多くの人がご存じだと思われます。
しかしながら、所得税の配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための条件を紹介する上で「配偶者控除とはどのようなものなのか?」について、どうしても外すことができない内容です。
そのため、ここではおさらいとして簡単に所得税の配偶者控除について紹介しておきます。
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
出典:国税庁 No.1191 配偶者控除 概要より引用
所得税の配偶者控除を受けるためには「所得税法上の控除対象配偶者」がいなければなりません。
そして、この控除対象配偶者にあてはまっている場合、所得税の配偶者控除を受けられることになります。

所得税の配偶者控除を受けるための条件【控除対象配偶者に該当する人】
所得税の配偶者控除を受けるためには、その年の12月31日の現況で、以下、4つの条件(要件)にすべてあてはまっていなければなりません。
なお、「その年の12月31日の現況」というのは、たとえば、令和4年度であれば「令和4年12月31日時点」ということです。
1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
出典:国税庁 No.1191 配偶者控除 控除対象配偶者となる人の範囲より引用

1.婚姻届を役所へ提出して受理された配偶者であること
2.配偶者控除を受ける人と日常生活を共にしていること
3.次項でわかりやすく解説します
4.事業などを営んでいる配偶者や親族の手伝いを普段から行って、これらの人から給与の支払いを一度も受けていないこと
【簡単確認】所得税の配偶者控除を受けるための所得要件について
所得税の配偶者控除を受けるためには、簡単にまとめた条件に加え、配偶者の所得について以下の条件を満たしていなければなりません。
上記の条件を満たしているのかどうか?については、配偶者の源泉徴収票または確定申告書を見ることで簡単に確認できます。
なお、働き方が多様化していることから、さまざまな形で収入を得ている人も多いと思われます。
そのため、考えられるパターンを考慮して簡単に確認できる方法をそれぞれ紹介します。
【給与収入のみの配偶者の場合】配偶者の源泉徴収票で確認

【確定申告をしている配偶者の場合】配偶者の確定申告書で確認

確定申告をしている配偶者は、複数の収入がある配偶者の場合や事業などを営んでおり、毎年確定申告をしている場合などが考えられます。
また、アルバイトやパートを掛け持ちして複数の会社などから給与の支払いを受けている場合も「確定申告書」で確認するようにしてください。
【FP相談事例も含む】所得税の配偶者控除を受けるための注意点
ここでは、所得税の配偶者控除を受けるための注意点について、FP相談事例も含めて紹介します。
所得税の配偶者控除は「性別」「年齢」「職業」が問われない
所得税の配偶者控除を受けるためには、すでに紹介した4つの条件をすべて満たしている必要があります。
そのため、性別や年齢、職業が配偶者控除を受けるために必要な条件になっていないため注意です。

配偶者控除を受ける人にも所得要件がある【配偶者控除の金額も紹介】
配偶者控除を受ける場合、配偶者控除を受ける人(本人)にも所得要件があります。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
出典:国税庁 No.1191 配偶者控除 控除対象配偶者となる人の範囲より引用

なお、配偶者控除の金額は、以下の通りです。
出典:国税庁 No.1191 配偶者控除 配偶者控除の金額より引用
配偶者控除を受ける人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が引下げられます。
そして、配偶者控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円を超えると控除対象配偶者がいたとしても、配偶者控除が受けられない点に注意が必要です。

障害者控除の適用もれ【配偶者だけでなく扶養親族も対象】
こちらは、FP相談事例からのものとなります。
仮に、配偶者が所得税法上の障害者にあてはまる場合、障害者控除を受けることができます。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。
出典:国税庁 No.1191 配偶者控除 配偶者控除の金額より引用
また、配偶者だけでなく、子どもや両親など扶養親族が所得税法上の障害者にあてはまる場合も障害者控除を受けることができます。

国税庁が親切に紹介している理由もわかる気がします
障害者控除が適用もれになる原因は、やはりそのような制度があることを知らない、要件を知らないといったことにつきると感じています。
以下、当事務所では所得税法上の障害者控除にかかる記事も公開しております。
何かしら心当たりがありそうな人は、所得税だけでなく住民税の節税対策につながる可能性があるため、合わせて読み進めてみることをおすすめします。

そのため、ライフプランやリタイアメントプランを考慮したとき、合わせ読みしたほうが良いと私は思う!
配偶者特別控除の適用もれ【配偶者控除が受けられない場合】
こちらも、FP相談事例からのものとなります。
仮に、配偶者控除を受けることができない場合であったとしても、配偶者特別控除を受けられる場合があります。
配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である方については、配偶者特別控除の適用を受けることができます。
出典:国税庁 No.1191 配偶者控除 その他より引用

FP相談の実務上、これも多いパターン!
【ポイントは1つ】所得税の配偶者特別控除を受けるための条件
所得税の配偶者特別控除を受けるための条件は、配偶者控除を受けるための条件とほとんど一緒です。
1.婚姻届を役所へ提出して受理された配偶者であること
2.配偶者特別控除を受ける人と日常生活を共にしていること
3.すでに紹介した確認方法で「源泉徴収票」または「確定申告書」を見て確認した結果、確認箇所の金額が「48万円超133万円以下」であること
4.事業などを営んでいる配偶者や親族の手伝いを普段から行って、これらの人から給与の支払いを一度も受けていないこと
ポイントは1つで、配偶者控除と配偶者特別控除の違いは所得要件です。
これまでの内容をまとめると、以下、吹き出しの通りとなります。

・48万円以下=配偶者控除
・48万円超133万円以下=配偶者特別控除
・133万円超=どちらも受けられない
【段階的に異なる】配偶者特別控除の控除金額
配偶者特別控除の控除金額は、配偶者控除のように一律ではなく、所得によって段階的に異なる特徴があります。
出典:国税庁 No.1195 配偶者特別控除 配偶者特別控除の控除額より引用
たとえば、夫の合計所得金額が800万円、妻の合計所得金額が103万円であったとします。
このとき、上記画像にあてはめますと、夫が受けられる配偶者特別控除は「31万円」であることがわかります。
おわりに【節税対策のご案内】
当事務所がお客様のご相談に応じ、これまでの実務経験から節税のポイントを簡単に紹介します。
・配偶者控除が受けられなくても、配偶者特別控除を受けることができないか?
・障害者控除や医療費控除など、ほかに受けられるものがないか?
・出産・育休・病気療養など、大きなライフイベントが発生したことはなかったか?
・大きなライフイベントの発生によって、受けられる控除をもらしていないか? など
実のところ、配偶者控除や配偶者特別控除にかかる節税対策も本ページで紹介する予定でした。
しかしながら、あまりにも長文になりそうなことから、本ページも合わせて2ページ構成にすることにしました。
2ページ目は、以下より確認することが可能です。
なお、所得税法では、過去に納めすぎた税金があった場合、税金を戻してもらえる手続きがあります。
・配偶者控除や配偶者特別控除をはじめとして、何かしらの控除をもらしていた
・過去に大きなライフイベントの発生によって、使える控除を使えていなかった など
これらのほか、類似するような事情がある場合、還付申告または更正の請求といった手続きをすることで、納めすぎた税金を戻してもらうことができる場合があります。
これも節税対策の1つといえるため、以下の関連記事も合わせて読み進めてみるのも良いでしょう。

内容がよかったと思った人は、SNSでのシェアをいただければ励みになります。
ご相談も随時受付しておりますので、ご検討をよろしくお願いいたします。
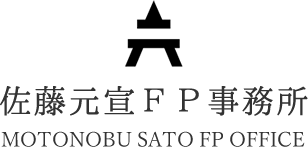











の注意点とポイントを独立系ファイナンシャルプランナー(FP)がわかりやすく解説します.jpg)