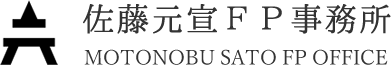本ページでは、iDeCoへ加入した場合に自分の節税効果がいくらになるのか?正しく自分で計算する方法をわかりやすく紹介します。
はじめに、iDeCoの加入を検討している人は、自分の節税効果がいくらになるのか?気になる人も多いと思います。
とはいえ、証券会社などが提供している節税シミュレーターを使っても計算されるのは概算金額(見込み額)です。
そのため、もっと細かく、正しく知りたいと感じている人も多いはずです。
そこで本ページでは、iDeCoの節税効果がいくらになるのか正しく自分で計算する方法をわかりやすく紹介します。
目次
【必ず確認してください】iDeCoに加入すると節税効果が得られる理由
iDeCoに加入すると節税効果を得られる理由は、1年間に掛けたiDeCoの掛金が所得控除の対象になるからです。
つまり、所得控除の金額を増やせることによって、所得税や住民税を少なくすることができます。

ちなみに、iDeCoの掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除と呼ばれる所得控除になります。
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。
出典:国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除 概要より引用
なお、iDeCoの掛金が小規模企業共済等掛金控除になることについて、国税庁では以下のように解説しています。

控除できる掛金は次の3つです。
(2)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
出典:国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金より一部抜粋引用
iDeCoは、別に「個人型確定拠出年金」とも呼ばれ、上記解説にある「個人型年金加入者掛金」がiDeCoの掛金になるわけです。
【1年間の掛金全額が対象】iDeCoの所得控除額について
iDeCoの掛金は、1年間で掛けた掛金の全額が所得控除の対象になります。
控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。
出典:国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金控除の金額より引用

したがって、1年間を通じてiDeCoに多くの掛金をかけることによって、大きな節税効果が得られることになります。
【簡単で正確】iDeCoの節税効果がいくらになるのか計算する方法
ここからは、iDeCoの節税効果がいくらになるのか?について、税金計算の流れに沿って紹介します。

ご自身の源泉徴収票を手元に用意し、以下、見出しの計算手順1から計算手順6に沿って行ってみてください。
計算手順1.所得金額の確認(源泉徴収票の赤枠)
まずは、ご自身の所得金額を源泉徴収票から確認します。
今回の場合、源泉徴収票の赤枠にある「給与所得控除後の金額」が所得金額となります。

計算手順2.所得控除の額の合計額(源泉徴収票の黄色枠)にiDeCoの年間掛金を足す
次に、所得控除の額の合計額(源泉徴収票の黄色枠)にiDeCoの年間掛金を足します。

計算手順3.課税所得金額を計算する
課税所得金額は、手順1の金額から手順2の金額を差し引いて計算します。

この246万円に所得税率を乗じることで、所得税が算出されます。
計算手順4.所得税額を計算する
計算手順3で計算した課税所得金額246万円を所得税の速算表にあてはめて所得税を計算します。
出典:国税庁 No.2260 所得税の税率 計算方法・計算式より引用
課税所得金額が246万円ですので、上記赤枠にある計算式にあてはめて所得税を計算すると以下のようになります。
246万円(課税所得金額)×10%(税率)-97,500円(控除額)=148,500円

計算手順5.復興特別所得税を計算する
復興特別所得税は、計算手順4で計算した所得税額に「2.1%」を掛けた金額です。
計算手順4で計算した所得税と計算手順5で計算した復興特別所得税を足した金額が、1年間で納めなければならない所得税等になります。

計算手順6.還付される税金の確認(iDeCoの節税効果)
最後に、還付される税金(iDeCoの節税効果)を確認します。
源泉徴収票の緑枠(源泉徴収税額)176,100円は、1年間で納めた所得税と復興特別所得税の合計金額です。
ただし、iDeCoの掛金を1年間で24万円支出したことによって、1年間で納めなければならない所得税等は151,618円(計算手順5で計算した金額)となりました。
つまり、多く税金を納めすぎていることを意味します。
したがって、1年間で納めなければならない所得税等から源泉徴収票の緑枠(源泉徴収税額)を差し引いた金額が還付される税金(iDeCoの節税効果)です。
今回の例では、iDeCoに月額2万円、年間24万円を支出したことによって、所得税の節税効果が24,482円得られました。
iDeCoは、長い期間に渡って積立していくものですから、長期間に渡る節税効果も大きなものになると考えられます。
【住民税はどうなる?】気になる住民税の節税効果について
iDeCoに1年間で支出した掛金は、所得税と住民税のどちらも節税効果が得られます。
ただし、所得税と住民税では、税金計算の仕組上、所得控除の金額が異なる特徴があります。
とはいえ、所得税だけではなく住民税の節税効果がどのくらいあるのか?知りたい人も多いことでしょう。
そこで、「あくまでも極端に乖離のある金額ではありません」が、概算住民税額と節税効果をここでは紹介します。
計算手順1.所得金額の確認(源泉徴収票の赤枠)
この手順は、先に紹介した所得税の計算手順1と全く同じです。

計算手順2.注意点あり!所得控除の額の合計額(源泉徴収票の黄色枠)にiDeCoの年間掛金を足す
次に、所得控除の額の合計額(源泉徴収票の黄色枠)にiDeCoの年間掛金を足します。
ただし、ここでは「基礎控除」のみ異なるものとして計算します。
・所得税の基礎控除:48万円
・住民税の基礎控除:43万円
ここでは、所得控除の合計額が161万円として住民税を計算します。

なお、配偶者控除や扶養控除など所得控除の種類によって所得税と住民税では、所得控除額が異なるものがたくさんあります。
そのため、住民税を計算するときは、どの所得控除がそれぞれいくらなのか?確認しておくことが大切です。
計算手順3.課税標準額を計算する
課税標準額は、手順1の金額から手順2の金額を差し引いて計算します。

この251万円に住民税の税率を乗じることで、概算住民税が算出されます。
計算手順4.住民税額を計算する
計算手順3で計算した課税標準額251万円に住民税の税率(一律10%)をかけて住民税を計算します。

住民税の節税効果を比較
iDeCoに加入しなかった場合の所得控除の額の合計額は「161万円」です。
これを基に住民税を計算しますと、以下のようになります。
課税標準額:436万円-161万円=275万円
271万円(課税標準額)×10%(税率)=275,000円(概算住民税額)
iDeCoに加入した場合の概算住民税額は「251,000円」でした。
したがって、iDeCoに加入した場合における住民税の節税効果は「24,000円(251,000円-275,000円)」となります。

【節税効果まとめ】所得税と住民税の節税効果はいくら?
今回の例において、iDeCoに月額2万円、年間24万円の掛金を支払った場合の所得税と住民税の節税効果をまとめます。
1.所得税の節税効果:年間24,482円
2.住民税の節税効果:年間24,000円
3.1年間の節税効果:48,482円(1と2の合計金額)
1年間で48,482円の節税効果について、感じ方は人それぞれ異なると思います。
しかしながら、納めなければならない税金は、私たちの家計にとってロスであることはいうまでもありません。
また、iDeCoは、将来の老後生活資金を準備するために活用するものです。
つまり、iDeCoへ加入して、将来の老後資金を貯めながら、無駄なお金のロスを避けられることは節税効果が大きい、小さいを別にして有効なお金の使い方といえます。

【年間上限あり】iDeCoの掛金は人によって異なる
iDeCoの掛金は、1年間に支出した全額が所得控除の対象です。
そのため、掛金が多ければ多いほど、所得税や住民税の節税効果も大きくなると考えられます。
ただし、iDeCoの掛金には、年間上限が設けられており、誰でも好きなだけ掛金を決めて支出できるわけではありません。

出典:iDeCo公式サイト iDeCoをはじめよう【ステップ2】掛金を決める!より引用
iDeCoの掛金は、現在の「国民年金の種別」によって、上限額が異なります。
国民年金の種別は、第1号被保険者から第3号被保険者まで3種類あり、上記画像の通りです。
また、厚生年金保険に加入している第2号被保険者は、勤務先に企業年金があるのか?ないのか?のほか、厚生年金基金に加入しているのかどうか?などによって、細かく分類されている点に注意が必要です。
【おわりに】iDeCoの節税効果とファイナンシャルプランニングを考える
本ページでは、iDeCoの節税効果がいくらになるのか正しく自分で計算する方法を紹介しました。
正確に細かくiDeCoの節税効果を知りたい人にとってみますと、参考になる情報だったのではないでしょうか?
ちなみに、iDeCoは、将来の老後生活資金を準備するために活用される制度です。
また、iDeCoは、自分で支出した掛金を「預金」「保険」「投資信託」から自由に選んで資産運用を行う特徴があります。
そのため、自身の資産運用のしかたによって、将来受け取ることになるiDeCoのお金は大きく変わることになります。
ファイナンシャルプランニングを考えますと、長い期間に渡って資産運用するiDeCoは、計画的、かつ、戦略的に活用していくことが大切です。
少なくとも、iDeCoに加入することで将来、いくらのお金が準備できるのか?いくらのお金を準備したいのか?は、あらかじめ明確にしておかなくてはなりません。
加えて、iDeCoで長い期間に渡って積立したお金は、将来受け取るときに、その受け取り方によって課される税金計算が全く異なります。
iDeCoは、節税対策として使えるメリットがある一方、ほかに考えなければならないことがたくさんあります。
なお、後日、大幅に加筆修正する予定ですが、以下、当事務所が公開している関連記事に参考となるものがあると思います。

内容がよかったと思った人は、SNSでのシェアや当事務所フェイスブックのフォローをいただければ励みになります。
ご相談も随時受付しておりますので、ご検討をよろしくお願いいたします。
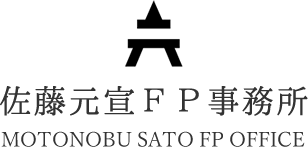


の注意点とポイントを独立系ファイナンシャルプランナー(FP)がわかりやすく解説します.jpg)

.jpg)
.jpg)