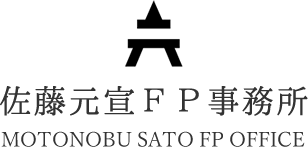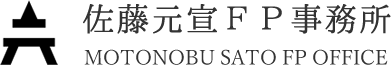本ページでは、つみたてNISA(積立 nisa)とは、どのような制度なのか、制度の特徴とおすすめの活用方法について、独立系ファイナンシャルプランナー(FP)ならではの考え方、および活用方法について合わせて紹介していきます。
(本ページは、2019年9月24日に投稿したものを2020年8月30日に加筆修正しております)

つみたてNISAの制度と活用方法について紹介していきます
はじめに、つみたてNISAとは、一言で申し上げると「ユーザーの皆さんの多くが不安に感じている教育資金や老後資金などのお金を長い時間をかけて無理なく貯められる方法」です。
そんなうまい話があるわけないと感じる人もおられるかもしれませんが、つみたてNISAは、それが十分可能であり、ポイントは、長い時間をかけてお金を大きく成長させるところにあります。
特に、結婚したばかりで将来が不安な人、子育て世帯で将来の教育資金や老後資金が不安な人には、ぜひ、最後まで読み進めていただきたいと思っています。
目次
つみたてNISA(積立nisa)とは
つみたてNISA(積立 nisa)とは、正式名称を「少額投資非課税制度」と言い、一定の金融商品に投資をして得た利益に対して税金がかからない制度です。
少額投資非課税制度と言えば、従来のNISAを思い浮かべる人も多いかもしれません。
しかしながら、つみたてNISA(積立nisa)という投資制度は、従来のNISAに加えて、平成30年1月から新たに始まった制度にあたり、これによって、NISA、もしくは、つみたてNISAのいずれかをご自身の選択によって選んで活用することができるようになっています。

どちらか1つをご自身が選んで活用します
一定の金融商品って何?
前項で、つみたてNISA(積立nisa)は、一定の金融商品に投資をして得た利益に対して税金がかからない制度と紹介しました。
ここで言う「一定の金融商品」とは、以下の通りです。
・金融庁が指定している投資信託
・金融庁が指定しているETF(上場投資信託)
一定の金融商品とは、金融庁が指定している投資信託、または、金融庁が指定しているETF(上場投資信託)の2種類です。
上記を見ますと、「金融庁が指定」という言葉にどうしても目がいってしまいがちです。
ただし、ここで重要なポイントは、つみたてNISA(積立nisa)で投資をすることができる金融商品は限られているところにあります。
加えて、つみたてNISA(積立nisa)で投資をすることができる金融商品の種類は、すべてではないところにあります。

つみたてNISA(積立 nisa)の投資対象商品について
つみたてNISA(積立 nisa)で投資をすることができる金融商品は、金融庁が指定している投資信託またはETF(上場投資信託)であることを紹介しました。
この時、おそらく多くの人は、つみたてNISA(積立nisa)の投資対象商品はどのくらいあるのか気になる人もおられると思います。
出典 金融庁 つみたてNISAの対象商品 つみたてNISA対象商品の概要についてより引用
令和2年6月29日時点において、つみたてNISA(積立nisa)で投資をすることができる商品は全部で182種類あるといった見方になります。
上記画像にある「公募投信」を金融庁が指定している投資信託、「ETF」を金融庁が指定しているETFと置き換えて差し支えありません。

つみたてNISA(積立nisa)の期待効果と非課税の仕組み
解説が重複致しますが、つみたてNISA(積立 nisa)とは、正式名称を「少額投資非課税制度」と言い、一定の金融商品に投資をして得た利益に対して税金がかからない制度です。
一定の金融商品とは、金融庁が指定している投資信託、または、金融庁が指定しているETFであることがわかりました。
ここでは、つみたてNISA(積立nisa)を活用することによって得られる期待効果と非課税の仕組みについて解説します。
つみたてNISA(積立nisa)で期待できる資産形成金額
出典 金融庁 資産運用シミュレーションを基に筆者試算
上記のシミュレーションは、つみたてNISAを20年間に渡って続け、毎月3万円ずつ積立投資をした例となります。

上記シミュレーションの結果をまとめると以下のようになります。
・20年間の積立金額(投資元本):720万円(3万円×12ヶ月×20年間)
・20年間の概算運用益(運用収益):約513.1万円
・20年後の資産形成金額(期待効果):約1233.1万円
20年間に渡って、毎月3万円ずつコツコツ継続して投資信託またはETFを買付したことによって、20年後に得られるお金(期待効果)は、約1233.1万円という見方になります。

非課税の仕組みも知ると、より期待効果がわかりやすくなります
つみたてNISA(積立nisa)における非課税の仕組み
つみたてNISA(積立nisa)は、一定の金融商品に投資をして得た利益に対して税金がかからない制度とお伝えしております。
つまり、2020年6月29日時点において、金融庁が指定している182種類ある商品のいずれかに投資をした場合、これらで得た利益(運用益)に対して税金がかからないことを意味します。
以下、前項のシミュレーション結果を基に、具体的につみたてNISA(積立nisa)における非課税の仕組みを解説していきます。
・20年間の積立金額(投資元本):720万円(3万円×12ヶ月×20年間)
・20年間の概算運用益(運用収益):約513.1万円
・20年後の資産形成金額(期待効果):約1233.1万円
まず、所得税法上、個人がその年の1月1日から12月31日までの1年間において、投資で得た利益には税金が課されます。
たとえば、投資信託やETFで利益を得た場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率を乗じた税金が差し引かれます。
つまり、先のシミュレーションの場合、約513.1万円の概算運用益に対して、20.315%の税率を乗じた税金が差し引かれることを意味します。

これを回避するのが、つみたてNISA!
つみたてNISA(積立nisa)を活用した場合、本来ならば徴収される税金を納めずに済みます。
つまり、先のシミュレーションの場合、つみたてNISAを活用すると20.315%の税金がかからないわけでありますから、104万円以上の無駄なお金を支払う必要がないことになります。
この結果、20年間で資産形成することができた約1233.1万円のお金を丸々手にすることができるわけです。
つみたてNISA(積立 nisa)の主な特徴まとめ
これまでの解説を読み進めていきますと、つみたてNISA(積立nisa)を私もやってみようかな?って感じた人もおそらく多いと思います。
ここでは、つみたてNISAの主な特徴について、金融庁が公開しているWEBサイトより引用して紹介し補足説明を加えていきます。
出典 金融庁 つみたてNISAの概要 つみたてNISAとはより引用
つみたてNISA(積立 nisa)を利用できる人は、20歳以上の人
つみたてNISA(積立 nisa)を利用できる人は、20歳以上の人であれば誰でも可能です。
ただし、つみたてNISAを始めるには、証券会社、銀行、インターネット証券会社を通じてNISA口座(つみたてNISAも兼ねています)を開設する必要があり、口座を開設する年の1月1日現在で20歳以上である必要があります。
したがって、たとえば、令和2年につみたてNISAを始めるのであれば、令和2年1月1日現在で20歳以上であればよいことになります。

つみたてNISA(積立 nisa)で税金がかからないものは、一定の投資信託などから得られる分配金や譲渡益
つみたてNISA(積立 nisa)で税金がかからないものは、一定の投資信託などから得られる分配金や譲渡益となります。

つみたてNISA(積立 nisa)の口座開設可能数は、1人1口座まで
つみたてNISAを始めるためには、先に説明をしましたように、証券会社、銀行、インターネット証券会社を通じてNISA口座(つみたてNISAも兼ねています)を開設する必要があります。
この時、つみたてNISA(積立 nisa)の口座開設可能数は、1人1口座までと決められています。
したがって、複数の金融機関で重複してつみたてNISA(積立nisa)の口座を開設することはできません。
なお、金融機関を変えたい場合は、変更手続きが別途必要になります。

金融機関によって取扱商品が異なるため、つみたてNISAを始める金融機関選びは、とても重要!
つみたてNISA(積立 nisa)で税金がかからない投資金額は、1年間で40万円が上限
つみたてNISA(積立 nisa)で税金がかからない投資金額は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で40万円が投資上限金額になっています。
・毎月3万円の積立:3万円×12ヶ月=36万円(OK)
・毎月4万円の積立:4万円×12ヶ月=48万円(NG)
1年間の投資金額が40万円を越えなければOKです。
ちなみに、会社員や公務員などの場合、夏季や冬季に支給される賞与(ボーナス)を考慮した投資も可能となっています。

重要な注意点
重要な注意点として、つみたてNISAの非課税投資枠は、翌年に繰り越すことができません。
毎月3万円の積立:3万円×12ヶ月=36万円(OK)
たとえば、毎月3万円ずつ積立を行った場合、年間投資金額は36万円となります。
この時、余った4万円分の投資枠を翌年以降に繰り越すことができません。
したがって、先のコメントでも紹介しましたように、長い時間をかけて大きな資産形成をするためには、できる限り、投資上限をフル活用することが望ましいと言えます。

資産形成するための目標金額や投資目的に合わせて戦略的な資産運用が肝!
つみたてNISA(積立 nisa)の非課税期間は、最長で20年間
つみたてNISA(積立 nisa)の非課税期間は、最長で20年間となっています。
たとえば、つみたてNISA(積立nisa)で資産運用した投資信託を10年後に現金化したとします。
この時、最長で20年間の範囲に収まっているため、運用益に対して税金がかかることはないといった意味になります。

タイムイズマネーっていうやつです!
つみたてNISA(積立 nisa)の投資可能期間は、2018年から2037年まで
つみたてNISA(積立 nisa)の投資可能期間は、2018年から2037年までとなっています。
いわゆる時限措置というものになりますが、おそらく、この期間は将来、延長されるものと筆者は予測しています。

重要なのは、つみたてNISAの特徴を活かした計画的な資産運用と資産形成を考えること!
つみたてNISA(積立 nisa)のおすすめ活用方法と考え方
つみたてNISA(積立nisa)の制度や主な特徴について解説をさせていただきました。
ここからは、つみたてNISA(積立nisa)でおすすめする活用方法と考え方について解説していきます。
おすすめの活用方法:子供の教育資金作り
つみたてNISA(積立nisa)でおすすめする1つ目の活用方法は、子供の教育資金作りです。
子供が誕生しますと、多くの親御さんは、子供の将来の教育資金について考える場合がほとんどです。
この時、多くの親御さんは学資保険の加入を検討することと思いますが、現状では、つみたてNISA(積立nisa)を活用する方が期待値が極めて高いと筆者は考えます。
この理由は、学資保険料と積立金額を比較し、それによって最終的に資産形成される金額を比較すれば簡単にわかるからです。

時間をいかに多くのお金に変えるのか考えると自ずとどちらが得策なのか簡単にご理解いただけます。
おすすめの活用方法:老後の資金作り
つみたてNISA(積立nisa)でおすすめする2つ目の活用方法は、老後の資金作りです。
老後の資金作りと言いますと、iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用したイメージが強いと思います。
しかしながら、iDeCoとつみたてNISA(積立nisa)は、いずれも併用することが可能なため、老後の資金作りを考える上でどちらも活用することはより効果的です。

無理をしない範囲で賢く活用することが、今と将来に大きな効果を与えます。
おすすめの活用方法:緊急予備資金作り
つみたてNISA(積立nisa)でおすすめする3つ目の活用方法は、緊急予備資金作りです。
はじめに、世界全体に大きな影響を与えた新型コロナウィルスによって、解雇や失業、収入減少といった損害を受けた人も少なくありません。
この時、緊急予備資金と呼ばれるお金をつみたてNISA(積立nisa)で作っておくことは効果的だと筆者は考えています。
ちなみに、緊急予備資金とは、不測の事態が起こった時に使うことができるお金のことを言います。

つみたてNISAは、新しい貯蓄方法の1つ
おすすめの活用方法:住宅ローンの繰り上げ返済資金作り
つみたてNISA(積立nisa)でおすすめする4つ目の活用方法は、住宅ローンの繰り上げ返済資金作りです。
特に、住宅ローンの返済について、公的年金が支給開始になる以降も続く人にとってみますと、老後生活を大きく圧迫してしまうリスクを抱えることになります。
また、会社員や公務員の人で退職金を住宅ローンの返済に充てた場合、老後のお金が目減りすることにもつながります。
そのため、長い時間をかけて住宅ローンの繰り上げ返済資金を作っておくことは、これらのリスクを回避できる効果が期待できます。

おすすめの活用方法:住宅の修繕資金作り
つみたてNISA(積立nisa)でおすすめする5つ目の活用方法は、住宅の修繕資金作りです。
住宅を購入して長い期間が経過しますと、当然のことながら建物が劣化・減価することによって修繕をしなければならない箇所が多く発生するリスクが高まります。
この時、リフォームまたはリノベーションする資金として、ある程度まとまった資金が必要になるため、この資金を準備するための対策としてつみたてNISA(積立nisa)を活用することができます。
長い時間をかけてコツコツ積立することによって、ローンの借入を新たにする必要がなく、老後生活資金を心配する必要もなくなる効果が期待できます。

特徴を活かした有効な活用をすると効果的です。
つみたてNISA(積立nisa)で資産運用を行うのが心配な人へ
つみたてNISA(積立nisa)を活用した資産運用や資産形成は効果的であることがこれまでの解説でご理解いただけたと思います。
とはいえ、投資が初めての人にとってみますと、損をすることが心配といった懸念を抱くことも少なくありません。
特に、新型コロナウィルスのような不測の事態が起こったことによる影響で損をするといったこともおそらく多くの人が考えることでしょう。
このような人は、以下、当事務所が公開している新型コロナウィルスによって生じたつみたてNISA(積立nisa)の影響について合わせて読み進めていただくことをおすすめします。

結論、新型コロナウィルスの影響は、一過性のものに過ぎません。
おわりに
本ページでは、つみたてNISA(積立 nisa)とは、どのような制度なのか、制度の特徴とおすすめの活用方法について解説させていただきました。
つみたてNISA(積立nisa)は、活用の幅が広く、使い方次第で大きな効果を期待できる投資制度であることは確かです。
その一方で、資産運用や資産形成をするための目的、つみたてNISA(積立nisa)の口座を開設する金融機関、つみたてNISA(積立nisa)で投資をする商品など、基本的な部分を明確にしておくことが大切です。
加えて、それぞれの人や世帯によって置かれている状況や考え方は異なります。
つまり、つみたてNISA(積立nisa)を考える上で、型にはまって簡単に考えることはその人にとって最も得策なものになり得ないということです。
ご自身またはその家族にとって、将来どのような資産形成ができているのが望ましいのか一度、考えてみることをおすすめします。

本ページが、ためになった人は「いいね」や「SNS」で発信していただけましたら励みになります。
当事務所では、つみたてNISA(積立nisa)のご相談について、全国対応可能でございます。
将来の資産運用や資産形成をしっかりと考えておきたいお客様は、ぜひ、当事務所の相談メニューについてご検討も合わせてお願い申し上げます。