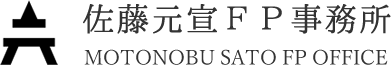本ページでは、リビングニーズ特約で受け取った生命保険金に所得税や相続税はかかるのかどうか?について紹介していきます。
はじめに、リビングニーズ特約は、医師から余命6ヶ月など余命宣告を受けた場合に、死亡保険金の「全部」または「一部」を生きている間に受け取ることができるものです。
また、リビングニーズ特約は、終身保険や定期保険などの生命保険に「無料」で付けられる特約であるほか、契約当初から自動的に付いている場合もあります。
現在や将来のファイナンシャルプランニングにおいて、病気や事故などによって医師から余命宣告を受けてしまうことがあるかもしれません。
このとき、リビングニーズ特約で受け取った生命保険金に所得税や相続税はかかるのか?気になる人も多いはずです。
そこで本ページでは、リビングニーズ特約と税金の取り扱いのほか、あらかじめ知っておきたいポイントも合わせて紹介していきます。
目次
【所得税はかからない】リビングニーズ特約で受け取った生命保険金と所得税の取り扱い
リビングニーズ特約で生命保険金を受け取った場合、受け取った保険金に所得税はかかりません。
これについて、国税庁では以下のように解説しています。
リビング・ニーズ特約による生前給付金は、死亡保険金の前払的な性格を有していますが、被保険者の余命が6か月以内と判断されたことを支払事由としており、死亡を支払事由とするものではないことからすれば、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものと認められます。疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われる保険金は、所得税法施行令第30条第1号《非課税とされる保険金、損害賠償金等》に掲げる「身体の傷害に基因して支払われる」保険金に該当するものと取り扱っており(所得税基本通達9-21)、その保険金は非課税所得となります。
出典:国税庁 リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金【回答要旨】より引用
リビングニーズ特約で受け取った生命保険金は、重度の疾病によって支払われた保険金と解されることがわかります。
このとき、重度の疾病によって支払われた生命保険金は所得税法上「非課税所得」として取り扱うことも確認できます。
このようなことから、リビングニーズ特約で受け取った生命保険金に対して所得税がかからないことになります。

【受け取った保険金が余った場合は注意】リビングニーズ特約で受け取った生命保険金と相続税の取り扱い
リビングニーズ特約で受け取った生命保険金に所得税や住民税がかかることはありません。
しかし、リビングニーズ特約で受け取った生命保険金によって、相続税がかかってしまったり、相続税の金額が増加してしまう懸念が生じます。

まずは、国税庁が解説しているリビングニーズ特約で受け取った生命保険金に対する注意喚起を確認していきましょう。
(注)生前給付金の受取人がその支払を受けた後(指定代理請求人が指定代理請求により支払を受けた場合を含みます。)にその受取人である被保険者が死亡した場合で、その受けた給付金のうち被保険者に係る入院費用等の支払に充てられた後の相続開始時点における残額は、死亡した被保険者に係る本来の相続財産として相続税の課税対象となります(この場合、相続税法第12条第1項第5号《相続税の非課税財産》の規定の適用はないことに注意してください。)。
出典:国税庁 リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金【回答要旨】より引用
上記、国税庁の解説より、リビングニーズ特約で受け取った生命保険金が余った場合、その余ったお金は相続税の課税対象になることがわかります。
つまり、相続税を計算するときの財産に、この余った受け取り保険金(現金預金)を含めて計算しなければなりません。
これによって、本来ならばかからない相続税がかかってしまったり、本来かかってしまう相続税の金額が増加してしまう懸念が生じます。

【死亡保険金の非課税適用なし】リビングニーズ特約で余った保険金は相続税の非課税財産にならない
相続税の計算をするときの財産には、死亡保険金の一部や死亡退職金の一部など、相続財産に含めなくてもよいものがあります。
しかし、国税庁の解説では、リビングニーズ特約で受け取った生命保険金のうち、余った保険金は相続税の非課税財産にならない注意喚起をしています。
ここで、すでに紹介した国税庁の解説をもう一度確認しておきます。
国税庁では、リビングニーズ特約で受け取った生命保険金は、死亡によって支払われた保険金ではないと解説しています。
そのため、リビングニーズ特約で受け取った生命保険金は、死亡保険金ではないため、相続税が一部かからない財産である死亡保険金にはあたらず、死亡保険金の非課税適用はないといってるわけです。

【具体例で簡単】リビングニーズ特約で受け取った生命保険金によって相続税がかかる場合とかからない場合
ここでは、具体例を紹介しながらリビングニーズ特約で受け取った生命保険金によって相続税がかかる場合とかからない場合を確認します。
なお、具体例における前提条件は、私の家族構成を基として以下の通りとします。

1.家族構成は、私(本人)・妻(配偶者)・3人の子どもとします
2.私は医師からの余命宣告によって、リビングニーズ特約で2,000万円の生命保険金を受け取ったものとします
3.受け取った生命保険金2,000万円を除いて、その他の資産(財産)として4,000万円があったものとします
4.簡単な紹介のため、上記以外の条件は加味しないものとします
まずは、相続税がかかるのかどうかの簡単な確認からスタートします。
【重要】相続税の基礎控除額の確認
相続税がかかるのかどうかを簡単に確認するには、相続税の基礎控除額がいくらなのか?を知らなければなりません。
上記の計算式にあてはめますと、私の財産が5,400万円(3,000万円+600万円×4人)以下であれば相続税がかからないと判定されます。
ちなみに、法定相続人は人によって異なりますが、私の場合は配偶者である妻と3人の子どもの4人が法定相続人です。
【リビングニーズ特約で受け取った生命保険金が影響】相続税がかかる場合
具体例の場合、5,400万円以下の財産であれば、残された家族が相続税を納める必要はありません。
しかし、リビングニーズ特約で2,000万円の生命保険金を受け取った結果、私の財産は6,000万円(2,000万円+4,000万円)です。
この結果、5,400万円を超えてしまったことにより相続税がかかると判定されます。
【死亡保険金として受け取ったらどうなる?】相続税がかからない場合
相続税の計算をするときの財産には、死亡保険金の一部や死亡退職金の一部など、相続財産に含めなくてもよいものがあることをお伝えしております。
ちなみに、遺族が死亡保険金を受け取った場合に、相続税の計算に含めなくてもよい死亡保険金は以下のように計算されます。
上記の計算式にあてはめますと、2,000万円(500万円×4人)の死亡保険金に対して相続税が課されることはありません。
つまり、リビングニーズ特約で2,000万円の生命保険金を受け取らず、死亡保険金として遺族が受け取った場合、私の財産は以下のように計算されます。
国税庁が注意喚起として解説していた内容はこのことを指しています。
つまり、死亡保険金として受け取った場合は、上記のような計算ができるもののリビングニーズ特約で受け取った生命保険金はNGということです。
この結果、5,400万円を超えなかったことにより相続税がかからないと判定されるわけです。

【贈与もNG】リビングニーズ特約の生命保険金は贈与しても相続税対策にならない
前項の具体例を見た人の中には、リビングニーズ特約で受け取った生命保険金を贈与したら相続税がかからなくて済むのでは?と思った人もいるでしょう。
しかし、リビングニーズ特約で受け取った生命保険金を贈与をしたとしても相続税対策にはなりません。
このように言い切れる理由は、以下、国税庁の解説を読むことでわかります。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
出典:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)概要より引用
上記、国税庁を解説を簡単に要約すると「死亡の日からさかのぼって3年以内の贈与は相続財産に含まれる」ということです。
どういったことなのかよくわからないと思いますので、先の具体例でポイントを紹介します。
1.家族構成は、私(本人)・妻(配偶者)・3人の子どもとします
2.私は医師からの余命宣告によって、リビングニーズ特約で2,000万円の生命保険金を受け取ったものとします
3.受け取った生命保険金2,000万円を除いて、その他の資産(財産)として4,000万円があったものとします
4.受け取った2,000万円について、3人の子どもへそれぞれ600万円ずつ贈与したとします
5.余命宣告から1年後に私が死亡してしまったものとします
6.簡単な紹介のため、上記以外の条件は加味しないものとします
まず、リビングニーズ特約で受け取った生命保険金を贈与したら相続税がかからなくて済むのでは?と思った人はこのような流れで考えたはずです。
1.2,000万円(リビングニーズ特約で受け取った生命保険金)-1,800万円(贈与分=3人×600万円)=200万円
2.4,000万円(その他の資産)+200万円(リビングニーズ特約で受け取った生命保険金の残り)=4,200万円
3.4,200万円(財産)が相続税の基礎控除額5,400万円よりも下回っているため相続税がかからない
しかし、この考え方は誤りで、国税庁の解説を考慮した正しい答えは以下のようになります。
1.2,000万円(リビングニーズ特約で受け取った生命保険金)-1,800万円(贈与分=3人×600万円)=200万円
2.4,000万円(その他の資産)+200万円(リビングニーズ特約で受け取った生命保険金の残り)+1,800万円(相続開始前3年以内の贈与分)=6,000万円
3.6,000万円(財産)が相続税の基礎控除額5,400万円よりも上回っているため相続税がかかる
結果を見ますと、リビングニーズ特約で受け取った生命保険金を贈与したとしても相続税対策になっていないことがわかります。
つまり、具体例の場合、贈与をしたとしても相続財産の金額を減らせておらず、リビングニーズ特約で受け取った生命保険金を贈与してもしなくても変わりません。
なぜ、このようなことになっているのか?
これは、相続税の納付を意図的に免れることを防止するためのルールになっているからです。
余命宣告を受けるということは、生い先が短く、近いうちに相続が開始になることを誰でも予測できます。
このとき、死亡した人の財産を死亡する前に滑り込みで贈与し、相続税の納付を免れることができれば、ほとんどの人が相続税を納めなくて済むことになるでしょう。
このようなことを防止するためのルールになっていることを考えますと、イメージがわきやすくわかりやすいのではないでしょうか?
【おわりに】リビングニーズ特約とファイナンシャルプランニングを考える
リビングニーズ特約で受け取った生命保険金に所得税がかかることはありません。
一方、相続税については、家族構成や資産額、リビングニーズ特約で受け取った生命保険金の金額など、さまざまな内容を精査しなければ判定することはできません。
ただし、そもそも相続税がかからない場合やリビングニーズ特約で受け取った生命保険金が余るようなことがない場合、相続税について極度に心配する必要はないでしょう。
今回、私自身が本ページを作成・公開し、自分がこの立場に置かれたとき、何を考えるだろう?と考えさせられました。
仮に、相続税がかかるとするならば、やはり相続税の納税準備資金として死亡保険金は遺族に渡るようにするでしょう。
一方、余生が短く、自分の人生に悔いを残したくないことを考えると、最後に何をすることが最適なのか?
実際に余命宣告を受けていないので、とても想像ができません。
ただ、ある程度まとまったお金が必要なことを最後にやりたいのであれば、家族の了解の下、リビングニーズ特約で生命保険金を受け取るかもしれません。
ちなみに、お墓や仏壇などが無い状態であれば、これらを生前中に購入しておくのもよいでしょう。
なぜならば、これらは「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ相続税がかからない非課税財産になるからです。
相続税がかかってしまう人、相続税がかかりそうな人、内容に興味がある人は、合わせて読み進めてみてはいかがでしょうか?

内容がよかったと思った人は、SNSでのシェアや当事務所フェイスブックのフォローをいただければ励みになります。
ご相談も随時受付しておりますので、ご検討をよろしくお願いいたします。
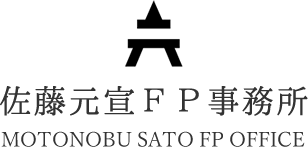



の注意点とポイントを独立系ファイナンシャルプランナー(FP)がわかりやすく解説します.jpg)


.jpg)