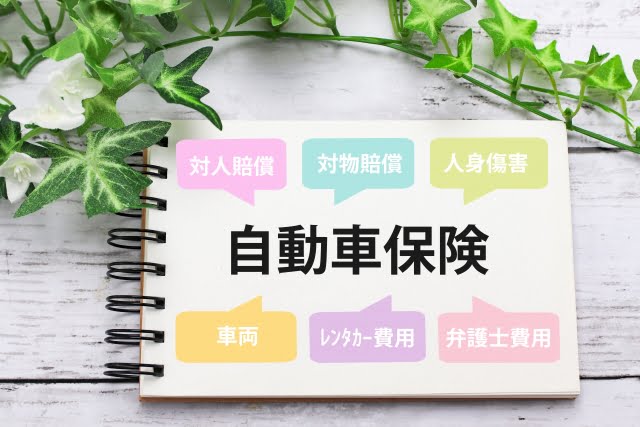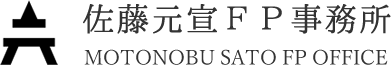本ページでは、自動車保険の等級とはどのようなものなのか?仕組みやポイントを紹介していきます。
なお、本ページは2020年1月19日に初めて公開したものを2022年9月15日に内容の加筆・修正・追記をしています。
はじめに、自動車保険には、強制的に加入しなければならない「自賠責保険」と任意で加入する「自動車保険」の2つがあります。
このとき、任意で加入する自動車保険には「自動車保険の等級」と呼ばれるものがあります。
自動車保険の等級は、自動車保険に加入している保険会社を問わず、私たちが実際に負担する保険料に直接関係する制度です。

目次
【制度の簡単解説】自動車保険の等級とは
自動車保険の等級とは、自動車保険に加入している人の保険料負担を公平にするため、事故歴に応じて自動車保険料の割引や割増を適用する制度のことです。
これを「ノンフリート等級制度」といいます。

自動車保険に限りませんが、そもそも「保険」は、加入するすべての人に対して「公平」でなければなりません。
ちなみに、自動車保険の場合における「公平」は、以下のように考えることができます。
・保険事故歴が多い人(自動車保険金の請求が多い人):保険料負担が多い
・保険事故歴がない・または少ない人(自動車保険金の請求をしなかった、または少ない人):保険料負担が少ない
保険金をもらった人が、保険金をもらわない人と同じ保険料負担ですと「不公平」ですよね?
そのため、保険料負担の公平性を保つために、自動車保険の等級によって区別しているわけです。

次では、自動車保険の等級について、仕組みやポイントを細かく紹介していきます。
【等級は20段階】自動車保険の等級の仕組みとポイント
自動車保険の等級は、負担する自動車保険料を公平にするための制度です。
このとき、自動車保険の等級は「20段階」にわけられ、等級の数字が大きいほど、自動車保険の等級が高い仕組みになっています。
出典:ソニー損保 等級制度の基礎知識 20段階に区分されていますより引用
自動車保険に初めて加入する場合の等級は基本的に6等級
自動車保険に初めて加入する場合、保険会社を問わず、自動車保険の等級は基本的に6等級からのスタートになります。
出典:ソニー損保 等級制度の基礎知識 初めは6等級からより引用
ただし、自動車保険の等級は、初めて自動車保険に加入した人だけが6等級になるとは限らない場合があります。
以下、簡単な一例です。
1.所有している自動車を「売却」した後、しばらく自動車を所有せず運転しない人
2.所有している自動車を「廃車」した後、しばらく自動車を所有せず運転しない人
3.海外へ勤務することになった人で、しばらく自動車を所有せず運転しない人
上記にあてはまる場合、重要な注意点があります。
それは「等級のリセット」です。
たとえば、自動車保険の等級が20等級だったとします。
そして、先に紹介した「1から3のいずれかにあてはまった」としましょう。
このとき、自動車保険の加入を引き続き行わず、一定の期間が経過した場合、20等級がリセットされ、新たに6等級からのスタートになってしまう場合があります。

【重要】しばらく自動車を運転しない予定がある場合は中断証明書の発行依頼を絶対に忘れないこと
高い等級をリセットされないようにするためには、自動車保険に加入している保険会社に対して「中断証明書の発行依頼」をする必要があります。
これによって、現在の自動車保険の等級が5年間や10年間など、一定期間に渡って維持することができます。
つまり、先の例の場合ですと、これまでの20等級が維持され、6等級からスタートする大きなデメリットを防止できるわけです。

【等級の上がり方)自動車保険の等級は、1年間に1等級ずつ上がる
自動車保険の等級は、1年間を通じて自動車保険の保険金を請求する事故(保険事故)がなかった場合、翌年度の自動車保険の等級は1等級アップします。
出典:ソニー損保 等級制度の基礎知識 1年間、保険を使った事故がなければ、次年度に等級が1つ上がりますより引用
つまり、自動車保険で高い等級になるためには、毎年、保険事故を起こさずに自動車保険を継続して契約していかなければなりません。
ちなみに、6等級からのスタートですと、最高等級(20等級)になるためには、「14年間」という長い期間を要します。

なお、自動車保険の等級が、一度に2等級や3等級アップするといった特殊な事情はありません。
その一方で、等級が下がる場合には「1等級ダウン事故」と「3等級ダウン事故」といったものがあります。

【保険事故】自動車保険の等級がダウンする「1等級ダウン事故」と「3等級ダウン事故」の違い
ここでは、自動車保険の等級がダウンする「1等級ダウン事故」と「3等級ダウン事故」の違いを簡単に紹介します。
紹介の流れを考慮し、まずは「1等級ダウン事故」からポイントを紹介します。
【偶発的(たまたま)がポイント】自動車保険の等級が1等級ダウンする保険事故とは
自動車保険の等級が1等級ダウンする保険事故は以下の通りです。
・火災・爆発(飛来中または落下中の物以外の他物との衝突・接触、転覆、墜落によるものを除きます。)
・盗難、騒じょう、労働争議
・台風、たつ巻、洪水、高潮
・落書、いたずら(ご契約のお車の運行によって生じたもの、他の自動車等との衝突・接触により生じたものを除きます。)
・窓ガラス破損(飛来中または落下中の物以外の他物との衝突・接触、ご契約のお車の転覆、墜落によるものを除きます。)
・飛来中または落下中の他物(飛び石、落石、ひょう等)との衝突
・その他偶然な事故によって生じた損害(他物との衝突・接触、転覆、墜落によるものを除きます。)
出典:三井ダイレクト損保 1等級ダウン事故(1等級ダウンする事故)より引用
上記の保険事故を一通り確認しますと、1等級ダウン事故は「予期せぬ偶発的な事故が原因の場合」であることがわかります。
自然災害による損害や飛び石によるガラスの破損などによって、保険金の請求をした場合、1等級ダウン事故の取り扱いになります。
【1等級ダウン事故以外】自動車保険の等級が3等級ダウンする保険事故とは
自動車保険の等級が3等級ダウンする保険事故は、先に紹介した1等級ダウンする保険事故にあてはまらない場合です。
わかりやすくいえば「他人を死傷させた」「他人のものを壊した」「自分の車を壊した」場合で、保険金請求した場合が3等級ダウン事故になります。

【ノーカウント事故】自動車保険を使っても等級が変わらない場合もある
自動車保険を使いますと、基本的には等級が下がります。
しかし、自動車保険を使っても等級が変わらない「ノーカウント事故」といったものもあります。
ノーカウント事故は、1年間を通じて保険事故がなかったものとして取り扱われ、具体的には以下のような場合です。
・搭乗者傷害保険
・人身傷害保険
・無保険車傷害特約
・弁護士費用補償特約
・ファミリーバイク特約
・ファミリー傷害特約
・被害者救済費用特約
・自転車賠償特約
出典:三井ダイレクト損保 ノーカウント事故(等級に影響しない事故)より引用
上記の補償について、自動車保険の保険金請求をしてお金を受け取ったとしてもノーカウント事故となります。
【ロードサービスもOK】ロードサービスを使った場合も等級が変わらない
自動車保険に加入しますと、バッテリー上がりやパンクなど自動車トラブルがあったときに助けてもらえるロードサービスがあります。
仮に、自動車トラブルによって自動車保険のロードサービスを使った場合も等級に影響を与えることはありません。
Q.ロードサービスを使うと等級は下がるの
A.いいえ、下がりません。ロードサービスは保険契約とは別に提供するサービスですので、ロードサービスを利用いただいてもノンフリート等級への影響はありません。
出典:ソニー損保 Q.ロードサービスを使うと等級は下がるのより引用
こちらは余談ですが、私がこれまでの人生で初めてロードサービスを使ったときに感じたことを紹介している関連記事があります。
ロードサービスを使っても、等級が変わらないことがわかっていたため、私は迷うことなくロードサービスを使いました。
万一の自動車トラブルの際に役立つと思われますので、合わせて読み進めてみることをおすすめします。
【おわりに】自動車保険の等級と保険事故から考えておかなければならないこと
自動車保険の保険金を請求しますと「保険事故」によって翌年度の自動車保険等級が下がってしまうことが基本的な取り扱いです。
しかし、ロードサービスを使った場合のように、等級が変わらない場合もあります。
そのため、自動車保険を使うことがあった場合、それによって等級がどのようになるのか?確認しておくことが大切です。
また、事故内容やご自身が置かれている等級によっては、自動車保険を使った方がよい場合と使わない方がよい場合もあるでしょう。
これは、事故(損害)の程度や等級が変化したことによる保険料の負担金額がどのくらい変わるのか?によって適切な判断が全く異なります。
したがって、どのようにすることが最適なのか具体的にお伝えすることはできません。
ただ、保険事故が発生した場合は、担当の保険社員や保険代理店をはじめ専門家を通じてどのようにしていくのが望ましいのか意見を聞いてみるのもよいでしょう。

内容がよかったと思った人は、SNSでのシェアや当事務所フェイスブックのフォローをいただければ励みになります。
ご相談も随時受付しておりますので、ご検討をよろしくお願いいたします。
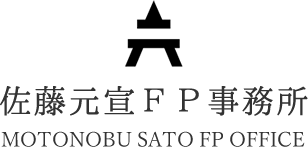



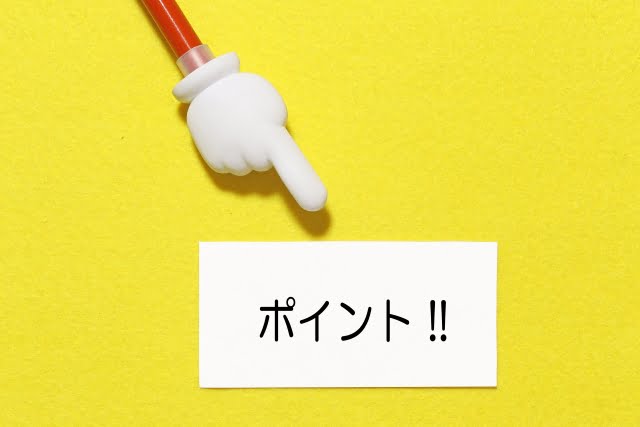




の注意点とポイントを独立系ファイナンシャルプランナー(FP)がわかりやすく解説します.jpg)