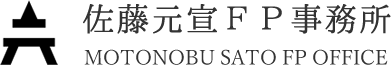本ページでは、相続における一次相続と二次相続の違いとはどこにあるのかについて解説しています。
また、二次相続の対策方法として有効な生命保険を活用した方法も合わせて解説していきます。
はじめに、相続対策や相続税対策をするにあたり、優先して考えるべきことがあります。
・死亡した人の財産を引き継ぐ相続人同士がもめずに円満な相続手続きが完了するにはどのようにしたらよいのか?
・相続税ができる限り発生しないような対策はどのようにしたらよいのか?
これらの相続対策や相続税対策を確実に行っていくためには、一次相続や二次相続と呼ばれる相続について知る必要があります。
これに加えて、一時相続と二次相続の具体的な対策方法も知っておくことが望ましいでしょう。
そこで本ページでは、一次相続と二次相続との違いをはじめ、具体的な相続および相続税対策の1つとして、生命保険を活用した二次相続の対策方法も合わせて解説していきます。
目次
【簡単に紹介】一次相続と二次相続の違いとは
まずは、一次相続と二次相続との違いについて簡単に紹介します。
一次相続とは、私たちが普段言っている「相続」のことをいいます。
たとえば、ご自身が子供の立場であったとし、両親のいずれかが死亡した場合に開始される相続が「一次相続」です。
一方、二次相続とは、一次相続で両親のいずれかが死亡した後、もう1人の親が死亡したことによって生じる相続のことをいいます。
つまり、今回の例では、両親の内、父親か母親の一方がすでに死亡しており、その後、親のいずれかが死亡した場合、二次相続になるといったイメージです。
これが、一次相続と二次相続の違いです。
実のところ、相続対策や相続税対策を行う上におきましては、一次相続よりも二次相続に焦点をあてて対策することが極めて重要といわれます。
この理由について、次項でわかりやすく解説を進めていきます。
【なぜ?どうして?】一次相続よりも二次相続の対策が重要とされる理由
一次相続よりも二次相続の対策が重要とされる理由は、「相続税の計算や控除による仕組み」や「相続財産の分け方にあたる遺産分割」が大きく関係しているためです。
これらがどのように関係しているのか、それぞれ個別に解説を進めます。
【1つ目の理由】相続税の計算や控除による仕組みについて
相続税の計算をする上で、相続税の基礎控除額と呼ばれる控除額があります。
相続税の基礎控除額は、相続税がそもそもかかるのか?かからないのか?を大まかに知るためにとても重要なものです。
ちなみに、相続税の基礎控除額には計算式があり、死亡した人の財産を引き継ぐ法定相続人の人数によって金額が異なります。
一例として、ご自身が子供の立場であったとし、父親・母親・弟の4人家族である場合で考えてみます。
上記例において、父親が死亡した場合の相続税の基礎控除額は以下のように計算されます。

この計算によってわかることは、仮に父親の財産が4,800万円以下であった場合、3人の法定相続人に相続税はかからないということです。
つまり、相続税がかかるのか?かからないのか?心配な人にとってみますと、相続税の基礎控除額を知ることは安心できるきっかけとなる1つの情報といえます。

一次相続と二次相続における相続税の基礎控除額の推移(変化)で考える
先の例を基に、一次相続と二次相続における相続税の基礎控除額の推移(変化)を確認してみましょう。
父親が死亡して一次相続が発生した場合の相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
母親が死亡して二次相続が発生した場合の相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
仮に、父親が死亡した場合の法定相続人は、父親の配偶者である母親、ご自身、弟の3人です。
しかし、母親が死亡し二次相続が開始しますと、法定相続人は、ご自身と弟の2人となります。
つまり、二次相続が開始するということは、法定相続人が1人減っていることによって、相続税の基礎控除額が少なくなってしまいます。
そのため、場合によっては、一次相続ではかからなかった相続税が、二次相続によって相続税がかかる原因になるかもしれません。
わかりやすいイメージとして、一時相続で母親が父親の財産を多額に相続した場合があげられます。
これによって、後に二次相続が開始され、相続税の基礎控除額を超える母親の財産を2人の子が相続することになりますと、相続税がかかる原因となります。
これが、一次相続よりも二次相続の対策が重要とされる1つ目の理由です。
【2つ目の理由】相続財産の分け方にあたる遺産分割
二次相続では、相続財産の分け方にあたる遺産分割でもめる可能性が生じます。
たとえば、高齢の母親が身体上の障害を抱えており、介護が必要な場合を考えてみます。
このような場合、毎月の介護費用をはじめ、場合によっては医療費も多くかかってしまう可能性が十分予測できます。
仮に、母親の年金収入や貯蓄で費用がまかなえない場合、経済的な支援として子がこれらの費用を負担することもあるでしょう。
また、介護が必要になりますと、子は経済的な負担だけではなく、肉体的・精神的な負担も合わせて抱えてしまうこともあります。
この負担を「片方の子だけが負担していた」としたら?

ご自身が、多くの負担を抱えながら最期まで母親の面倒を見ていたとしたらどうでしょう?
少なくとも、母親の財産を相続するにあたり、これらの負担を考慮した上で自分の方が多少なりとも多くもらえるべきだと感じないでしょうか?
相続人との話し合いでうまくまとまれば何ら問題は生じません。
しかし、人情がわからない相続人や自分のことしか考えない物分かりが悪い相続人であれば、相続でもめてしまう可能性は否めません。
二次相続対策であらかじめ考えておきたいこと
今回の例において、一次相続では、両親のいずれかが生存しています。
そのため、一次相続において、死亡した人の遺言や生存している親のことを考えた遺産分割がされやすい傾向にあります。
しかしながら、二次相続になりますと、両親がいずれも死亡し、いわば、子供たちだけで遺産分割することになるのが通常です。
このとき、先に紹介したような事情がありますと、遺産分割でもめてしまう可能性が大きくなります。
これが、一次相続よりも二次相続の対策が重要とされる2つ目の理由にあたります。
そのため、二次相続対策といった観点では、以下のようなことをあらかじめ考えておきたいものです。
・生前から家族で後の相続などについて話し合っておく
・母親が生前贈与を活用してもめない相続を実現するための対策をする
・母親が遺言書を作成しておく など

【注意点】二次相続では、配偶者の税額の軽減が活用できない
一次相続や二次相続の対策を考える場合、すでに紹介した相続税の基礎控除額のほかに、「配偶者の税額の軽減」と呼ばれるものも考えておく必要があります。
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。
1.1億6千万円
2.配偶者の法定相続分相当額
出典 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減 1 制度の概要より引用
国税庁の解説を簡単に要約すると、死亡した人の配偶者は、1億6,000万円以下の財産を相続した場合、相続税がかかることはありません。
つまり、この部分だけを考慮して、一次相続で配偶者が多くの財産を相続しますと、配偶者や子は相続税を納めなくて済む可能性があります。
しかしながら、大きな財産を相続した配偶者が死亡した後の二次相続はどのようになるでしょう?
たとえば、父親が死亡し、1億円の財産を母親が相続したとして考えてみましょう。
これまで紹介した家族構成の場合、二次相続の開始によって財産を相続するのは2人の子です。
つまり、死亡した人の配偶者ではないため、「配偶者の税額の軽減」は使うことができません。
一方、母親が一次相続で1億円を相続したものが、子どもたちや孫の後先を考えてほぼそのまま残っていたらどうでしょう?
相続税の基礎控除額4,200万円(3,000万円+(600万円×2人)を超えているため、2人の子は、多くの相続税を納めなければならなくなる可能性が生じます。

【二次相続対策】生命保険を活用した二次相続の対策方法
二次相続の対策方法には、生前贈与を活用したり、遺言書を作成しておく対策方法があります。
これらのほかにも生命保険を活用した二次相続の対策方法も効果的です。
まずは、二次相続の対策で生命保険を活用した場合に得られる効果について、以下、大まかにポイントを紹介しておきます。
1.生命保険の契約で設定した保険金受取人を配偶者ではなく子供にすることによって、一次相続および二次相続でかかるトータルの相続税額を軽減することができる
2.生命保険の保険契約を工夫することによって、二次相続において死亡保険金への課税を軽減させることができる
3.死亡した人の配偶者も生命保険に加入することで、二次相続においても相続税の非課税制度を活用することができる
上記3つのポイントが、それぞれどのように二次相続の対策に効果をもたらすことになるのか、個別にポイントの解説を進めていきます。
生命保険の契約で設定した保険金受取人を配偶者ではなく子供にすることによって、一次相続および二次相続でかかるトータルの相続税額を軽減することができる
仮に、死亡した人の相続財産が多額であることによって、相続税対策を取っていたとしても、一次相続および二次相続のいずれにおいても相続税がかかってしまうこともあります。
このような場合、生命保険の保険金受取人を配偶者ではなく子供にしておくことによって、一次相続および二次相続でかかるトータルの相続税額を低くすることができる効果が得られます。
これは、すでに解説をした、相続税における「配偶者の税額の軽減」の効果が極めて大きい理由が関係しています。
仮に、生命保険の死亡保険金を受け取る人が、子供ではなく配偶者であった場合、後程解説する相続税の非課税制度と重複することによって、前述した「配偶者の税額の軽減」の効果が低くなってしまいます。
そのため、生命保険を活用した二次相続の対策方法の1つとして、保険金受取人を配偶者ではなく子供にすることで、より大きな節税効果が期待できます。
生命保険の保険契約を工夫することによって、二次相続において死亡保険金への課税を軽減させることができる
生命保険の保険契約を締結する際、保険契約者、被保険者、保険金受取人といった三者を必ず決定する必要があるのですが、この三者間を工夫して変更することによって、二次相続における対策を行うことができます。
この時、重要な注意点として、生命保険の保障対象にあたる「被保険者」は変更することができないため、あくまでも「保険契約者」と「保険金受取人」を工夫して変更することによって二次相続における対策をすることに留意して下さい。
具体的な対策方法として、たとえば、保険契約者と保険金受取人を父親、被保険者が母親の生命保険に加入します。
仮に、父親が死亡した場合、被保険者が母親でありますから、この保険契約が無くなることはなく、保険契約者と保険金受取人を変更することで足ります。
この時、保険契約者を母親、保険金受取人を子供に変更することで、保険契約者と被保険者が母親、保険金受取人が子供となり、これで二次相続対策が行えることになります。
母親が先に死亡した場合
仮に、保険契約者と保険金受取人を父親、被保険者が母親の生命保険に加入している状態で、母親が先に死亡してしまった場合、二次相続対策が行われないのでは?と感じるユーザーの皆さまもおられるでしょう。
確かに、上記保険契約で母親が先に死亡した場合、死亡保険金を受け取るのは父親にあたり、この受け取った死亡保険金は、一時所得として、所得税の課税対象になります。
しかしながら、実のところ、一時所得を活用した生命保険の相続対策もあり、この対策方法が、世帯全体で相続税を考えた時、より多くの効果を得られる場合があるのです。
何が言いたいのか。
相続対策や相続税対策というのは、財産状況、家族構成、本人および家族の希望といった多くのことを考慮し、あらゆる角度からシミュレーションをしたり比較検討を行った上で、その人にとって最適な対策方法が見つかるのです。
したがって、こちらの方法は、二次相続対策のための1つの方法に過ぎないことをユーザーの皆さまにはご理解いただく必要があります。
死亡した人の配偶者も生命保険に加入することで、二次相続においても相続税の非課税制度を活用することができる
一次相続と二次相続の対策を考える上で活用される生命保険には、相続税法で定められている「死亡保険金の非課税制度」が活用できるメリットがあります。
相続税法で定められている「死亡保険金の非課税制度」とは、「500万円×法定相続人の数」で計算した死亡保険金は、相続税の計算をする上で財産の金額に含めないといった制度です。
これだけではイメージがわきづらいと思いますので、仮に、ご自身が子供の立場であったとし、父親・母親・弟の4人家族である場合で考えてみます。
たとえば、父親が死亡し、生命保険の死亡保険金として1,500万円を保険会社から受け取った場合、法定相続人は、配偶者である母親とご自身および弟の3人です。
この時、「500万円×3人=1,500万円」までの死亡保険金を受け取ったとしても相続税がかからないことになりますので、今回受け取った死亡保険金1,500万円に対して相続税はかからないと判定されます。
これを一次相続だけではなく二次相続といった対策で考えますと、父親および母親の両方が生命保険に加入していることによって、一次相続および二次相続が発生した場合でも、相続税の非課税制度を活用できることになります。
また、次項の「生命保険を活用した二次相続の対策における注意点」で触れますが、配偶者の生活保障を確保する目的で死亡保険金を活用することもできるため、相続税対策と生活保障といった2つの側面から考えても効果的な対策方法と言えます。
生命保険を活用した二次相続の対策における注意点とは
生命保険を活用した二次相続の対策における注意点には、「配偶者の生活保障」と「相続が発生する順番」があげられます。
これまでの解説では、主に、相続税対策としての側面が強かったわけですが、仮に、死亡した人の配偶者が保有している資産が乏しい場合、生命保険の死亡保険金は、配偶者のこれからの生活保障として活用されることが望ましいと考えられます。
そのため、配偶者や子供といった相続人の経済状況がどのような状態なのかによって、二次相続における相続税対策以外の部分から検討が必要になる点に注意しなければなりません。
また、当初、生命保険を活用した二次相続の対策を行っていたとしても、時として、相続が開始となる順番が逆になる場合も考えられます。
たとえば、父親が先に死亡し、二次相続として母親が死亡した場合の対策を取っていたのにも関わらず、母親が先に死亡した場合といったイメージです。
このように、相続が発生する順番が変わってしまうことによって、これまで行ってきた二次相続の対策が効果的ではなくなるリスクも踏まえた対策が時として必要になる場合があります。
すでに解説をしましたが、一例として、死亡した人の配偶者も生命保険に加入しておくことで、どちらが先に死亡したとしても相続税対策や配偶者の生活保障といった対策が行えるわけでありますから、家計の懐事情を精査した上で、生命保険の加入を検討されてみるのもよいのではないかと筆者は考えます。
おわりに
本ページでは、一次相続と二次相続の違いや生命保険を活用した二次相続の対策方法について解説をしました。
本ページの冒頭では、相続対策や相続税対策をするにあたり、優先して考えるべきこととして、「死亡した人の相続財産を引き継ぐ相続人同士がもめずに円満な相続手続きが完了するにはどのようにしたらよいのか?」、「相続税ができる限り発生しないような対策はどのようにしたらよいのか?」をお伝えしましたが、生命保険を活用した二次相続の対策方法は、いずれの対策も満たしている方法の1つであると言い切ることができます。
相続対策や相続税対策を考える上で、生命保険を活用する対策方法のほかにも贈与を活用した対策方法や不動産を活用した対策方法など、様々な方法があるのは確かですが、生命保険を活用した対策方法は、遺族が生活していくための生活保障としての大切な役割や相続税を確実に納付するための納税準備金対策として活用できることも押さえておきたいポイントとも言えます。
なお、生命保険を活用した一次相続や二次相続の対策は、保険料を負担することによるキャッシュが支出されるデメリットがどうしても生じてしまいますが、このデメリットを補う役割が贈与を活用した相続対策にあたります。
そのため、本ページでは、生命保険を活用した相続や相続税対策について解説をしましたが、相続対策をこれから行っていくユーザーの皆さまは、贈与や生命保険などを賢く活用した相続対策を行っていくことが望ましいと言えるでしょう。![]()
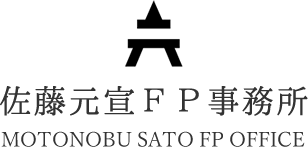



が良い理由を客観的に紹介.jpg)