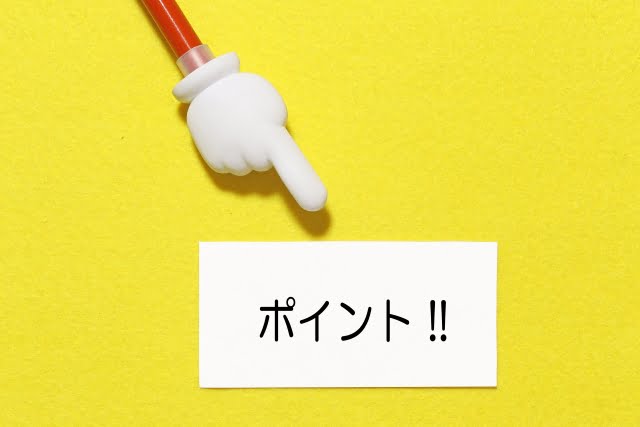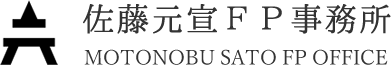本ページでは、日本学生支援機構の給付型奨学金について、制度のポイントをわかりやすく解説します。
はじめに、給付型奨学金は、その名前の通り給付される奨学金のことをいいます。
つまり、ただでもらえる奨学金を意味し、いわば「返済なしの奨学金」ともいえます。
ここだけを見ますと、子どもが進学し学費がかかる世帯からしますと、誰でも給付型奨学金をもらいたいと思うのは当然のことです。
しかし、給付型奨学金の制度には、さまざまな必要条件があります。

そこで本ページでは、日本学生支援機構の給付型奨学金について、制度の詳細をわかりやすく解説していきます。
目次
【返済なしの奨学金】日本学生支援機構の給付型奨学金とは
日本学生支援機構の給付型奨学金とは、家庭の経済的理由によって子どもが大学や専門学校などへの進学をあきらめないようにするための支援制度です。
ちなみに、給付型奨学金を受けることになりますと、進学する大学や専門学校などの授業料や入学金が「免除または減額」されるメリットもあります。
これらのことから、子どもが進学する場合は、給付型奨学金を受けられるのかどうか?を必ず確認しておくことがとても大切です。

【令和4年度】給付型奨学金を申し込みできる人
返済不要の給付型奨学金は、誰でも申し込みできるわけではありません。
ちなみに、日本学生支援機構では、進学前に給付型奨学金の申し込み資格がある人について、以下のように解説しています。
次の(1)または(2)のいずれかに該当する人が申し込めます。
(1)2023年3月に高等学校等(本科)を卒業予定の人
(2)高等学校等(本科)を卒業後2年以内の人
※2022年秋季に卒業予定の人も対象になります。
出典:日本学生支援機構 進学前(予約採用)の給付奨学金の申込資格より引用
上記解説より、給付型奨学金を申し込みできる人は「高校などを卒業予定の人」か「高校をすでに卒業して2年以内の人」のいずれかです。
そのため、これらいずれかの申し込み条件にあてはまっていない場合、そもそも給付型奨学金をもらうことはできません。

参考:日本学生支援機構 進学後(在学採用)の給付奨学金の申込資格
【被災・家計急変】偶発的な特殊事情によって給付型奨学金を申し込みできる人
日本学生支援機構の給付型奨学金を申し込みできる人は「高校などを卒業予定の人」か「高校をすでに卒業して2年以内の人」のいずれかでした。
しかし、被災や家計急変など、偶発的な特殊事情が起こった場合、給付型奨学金を申し込みすることができます。

具体的な特殊事情は以下の通りです。
家計急変により給付奨学金の対象となるのは、次の1から6のいずれかに該当する場合です。
1:両親の一方(または両方)が死亡した場合
2:両親の一方(または両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難な場合
3:両親の一方(または両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)した場合
4:両親が震災、火災、風水害などに被災した場合で、次の(1)(2)のいずれかに該当した場合
(1)上記1から3のいずれかに該当した場合
(2)被災により、両親の一方(または両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生した場合
5:新型コロナウイルス感染症の影響により減収した場合
6:家庭内暴力(いわゆるDV)から避難等した場合
上記6つの中で、「3」については注意が必要です。
「3」は、両親のどちらか、または両方が失業した場合ではあるものの、自己都合退職は対象外であることがわかります。
非自発的失業となっていることから、いわゆる「倒産」や「解雇」など特殊な事情によって失業(失職)した場合でなければ対象にならない点に注意が必要です。

【3つの必要条件】給付型奨学金をもらうために必要な条件
日本学生支援機構の給付型奨学金をもらうためには、すでに紹介した申し込み条件を満たしている必要があります。
これに加え、これから紹介する3つの必要条件をすべて満たしていなければなりません。

【1つ目の必要条件】学力基準を満たしているかどうか
給付型奨学金をもらうための1つ目の必要条件は、学力基準を満たしているかどうか?です。
ここでいう「学力基準」について、日本学生支援機構では以下のように解説しています。
以下の1.もしくは2.のいずれかに該当する必要があります。
1.高等学校等における全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること(※1)
2.将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有すること(※2)
※1専修学校の高等課程の生徒等は、これに準ずる学修成績となります。
※2学修意欲等の確認は、高等学校等において面談の実施又はレポートの提出等により行います。
出典:日本学生支援機構 進学前(予約採用)の給付奨学金の学力基準より引用
高校での成績が、5段階評価で平均3.5以上の学力があれば給付型奨学金の学力基準を満たしていることが確認できます。
仮に、上記基準を満たしていなかったとしても、いわゆる「本人のやる気」があれば学力基準を満たしていると解することもできます。

「2」の学力基準は「1」の基準に比べて曖昧となっており、面談やレポート提出の結果で判断する人の裁量に左右されるといえそうです。
【2つ目の必要条件】収入基準を満たしているかどうか
給付型奨学金をもらうための2つ目の必要条件は、収入基準を満たしているかどうか?です。
はじめに、給付型奨学金をもらうための収入基準には「第1区分」「第2区分」「第3区分」といった3つの区分があります。
そして、これら3つの区分のいずれかにあてはまった場合、給付型奨学金をもらうための「収入基準」を満たしていることになります。

なお、3つの区分は、以下の通りです。
第1区分:申込者本人(子ども)と両親の市町村民税所得割が非課税である場合
第2区分:申込者本人(子ども)と両親の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満である場合
第3区分:申込者本人(子ども)と両親の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満である場合
上記、支給額算定基準額は、以下の計算式によって求められます。
何が何だかまったく意味がわからないというのが本音であるはずです。
また、給付型奨学金の収入基準判定は、扶養している人の人数や障害者なのかどうか?に加え、住んでいる市町村による違いもあります。

このような理由から「進学資金シミュレーター」で収入基準に該当するかおおよその確認をする方が簡単でわかりやすいのです。
【使い方マニュアルも合わせて紹介】進学資金シミュレーターで収入基準を満たしているか確認
給付型奨学金の収入基準を満たしているかどうかを知りたい人は多いはずです。
しかしながら、その答えを知るための意味が全くわけがわからないところが多いというのも事実です。
だからこそ、進学資金シミュレーターを使って収入基準に該当するかおおよその確認をする方が簡単でおすすめといえます。

そして、進学資金シミュレーターの使い方マニュアルは、以下の参考ページでご確認ください。

【3つ目の必要条件】資産基準を満たしているかどうか
給付型奨学金をもらうための3つ目の必要条件は、資産基準を満たしているかどうか?です。
まず、ここでいう「資産」には、資産に含まれるものと資産に含まれないものがあります。
資産に含まれるもの:現金・預貯金・有価証券(投資信託・株式など)・投資用資産(金・銀など)
資産に含まれないもの:不動産(土地・建物など)・貯蓄型の生命保険・学資保険
資産基準は、申込者本人(子ども)と両親の上記「資産に含まれるもの」の合計金額が2,000万円未満の場合に満たしていることになります。
なお、片親の場合、1,250万円未満であるとき、資産基準の条件を満たすことになります。
ちなみに、両親がいない場合で、おじやおば、祖父母が生計維持者の場合、両親をこれらの人へ置き換えて読み進めてください。

【給付型奨学金の金額】もらえる金額は進学する学校や通学のしかたなどで変わる
給付型奨学金の申し込み条件を満たしている人にとって、実際にいくらもらえるのか気になる人は多いはずです。
ただ、給付型奨学金でもらえる金額というのは、すべての人が同額ではなく、進学する学校や通学のしかたによって異なる特徴があります。
また、すでに紹介した「収入基準=第1区分から第3区分」によっても金額が変わります。

【毎月振り込まれる金額】国公立の場合
出典:日本学生支援機構 給付奨学金の支給額【国公立の場合】より引用
自宅通学にあるかっこ書きの金額は、生活保護(扶助の種類を問いません)を受けている両親と同居している人または社会的養護を必要とする人で児童養護施設などから通学する人が給付される奨学金の金額です。
なお、毎月振り込まれる奨学金は、原則として毎月11日に振り込まれます。
ただし、4月と5月は日付が異なるほか、11日が土日祝日の場合、金融機関の前営業日となります。

【毎月振り込まれる金額】私立の場合
出典:日本学生支援機構 給付奨学金の支給額【私立の場合】より引用
自宅通学にあるかっこ書きの金額や振り込みされる日は、先に紹介した国公立の場合と同じです。
【1年間で1回振り込まれる金額】通信教育課程の場合
出典:日本学生支援機構 給付奨学金の支給額【2.通信教育課程】より引用
通信教育課程の給付型奨学金は、毎月ではなく「年1回」振り込まれる点に注意が必要です。
【給付型奨学金と税金】もらった奨学金に税金はかかる?
給付型奨学金をもらいますと、このもらった奨学金に対して税金がかかるのか気になる人もいると思います。
結論から申し上げますと、給付型奨学金に税金がかかることはありません。
ちなみに、国税庁のWEBサイトでも「学資金および扶養義務を履行するために給付される金品(所法9①十五、所令29)」は、所得税法における非課税所得だと解説しています。
参考:国税庁 No.2011 課税される所得と非課税所得 非課税所得(その他)

【給付型と貸与型の併用OK】給付型奨学金と貸与型奨学金はどちらも申し込みできる
日本学生支援機構の奨学金には、給付型奨学金と貸与型奨学金の2種類があります。
これらの奨学金は、いずれも申し込み条件や必要条件にあてはまっている場合、どちらも併用して利用することができます。
特に、給付型奨学金をもらえる場合、貸与型奨学金で申し込みする金額は、多少なりとも少なくて済むはずです。
そのため、貸与型奨学金を申し込みする前に、すでに紹介した給付型奨学金のシミュレーターで、給付対象になるかどうかを確認しておくことが大切です。
【おわりに】日本学生支援機構の給付型奨学金について私が思うこと
日本学生支援機構の給付型奨学金は、申し込み条件を満たしており、3つの必要条件を満たしていなければもらうことができません。
しかし、仮に給付型奨学金をもらえなかったとしても、被災・家計急変による申し込みができることを知っておく必要があります。
なぜならば、ファイナンシャルプランニングにおいて、いつ、何が起こるかわからないからです。
たとえば、大学などへ子どもが在学中に被災・家計急変にあてはまるようなことが起こってしまうかもしれません。
このとき、給付型奨学金に申し込むことができるのを知っているのと知らないのでは大きな差があることはいうまでもないでしょう。
また、これは親だけでなく子(本人)も知っておく必要があることです。
被災・家計急変による給付型奨学金の申し込みは、ある意味「リスクヘッジ対策」の1つともいえます。
だからこそ、親子で情報共有してそれぞれが知っておかなければならないことだと私は思うのです。
子どもからしますと、進学先の学校で知り合った大切な友達や知人が被災や家計急変によって人生が変わる岐路に立たされてしまう可能性もあるでしょう。
このようなとき、ちょっとした気遣いでその人の人生が大きく変わるきっかけになるかもしれません。
最後に、今回のページでは、あえて給付型奨学金の申し込み手続きや必要書類を解説しませんでした。
このようにしたのは、まずもって給付型奨学金の対象になるのかどうか?を知る必要があるからです。
結果として、対象になった場合、自ずと手続き方法や必要書類を調べて確認します。
このとき、学校や日本学生支援機構へこれらを確認することが容易に考えられるため、あえて本ページで記載する必要性はないのではないか?と判断しました。
なお、日本学生支援機構では、給付型奨学金のシミュレーション結果がすべてではないとしています。
つまり、シミュレーション結果がNGであったとしても、OKであったとしても最終的な可否判断は機構が決定するということです。
したがいまして、シミュレーションは目安になるものではあるものの、学校や日本学生支援機構とやり取りをしながら一歩ずつ話を進めていくことが大切になるといえます。
ちなみに、親にとって子どもの奨学金を将来、資金援助したり一括返済したいと考えている人もいると思います。
このような人は、以下の関連記事も合わせて読み進めていただくことをおすすめします。
特に、これから奨学金の申し込みをする予定の人には、先々を考える上で参考になる内容なのではないか?と思っています。

内容がよかったと思った人は、SNSでのシェアや当事務所フェイスブックのフォローをいただければ励みになります。
ご相談も随時受付しておりますので、ご検討をよろしくお願いいたします。
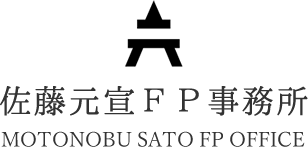




の注意点とポイントを独立系ファイナンシャルプランナー(FP)がわかりやすく解説します.jpg)





.jpg)