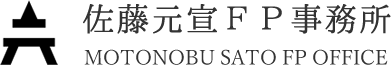本ページでは、出産費用で医療費控除の対象となるものと医療費控除の対象にならないものについて紹介していきます。
このページは、お客様からの相談依頼に基づき、これから出産予定のお客様に節税対策の1つとしてお話させていただいたことを踏まえたものとなります。
これから出産予定の人、今後出産する予定がある人、すでに出産を終えて「5年間」経過していない人にとっては役立つ内容だと思います。
目次
出産費用は基本的に医療費控除の対象になる
はじめに、出産費用は基本的に医療費控除の対象になります。
ちなみに、医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間で、実際に支出した医療費が高額になった場合、確定申告をすることによって納めるべき所得税および住民税を少なくできる税制度です。
ただし、医療費控除の対象となる出産費用には、対象となるものとならないものがあります。
具体的にどのような出産費用が対象になるのか?以下、わかりやすく紹介します。
医療費控除の対象となる出産費用
医療費控除の対象となる出産費用の具体例として、以下のようなものがあります。
・妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用
・妊娠と診断されてからの定期検診や検査などを受診するための通院費用(注意点は後ほど)
・分娩費用(注意点は後ほど)
・出産した後、病院に対して支払う入院中の食事代(注意点は後ほど)

ただし、例外として医療費控除の対象にならない出産費用もあるため、以下、注意点として紹介します。
医療費控除の対象とならない出産費用(注意点)
医療費控除の対象とならない出産費用の具体例として、以下のようなものがあります。
・自己所有の自動車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
・いわゆる「里帰り出産」にかかる交通費
・出産前の入院に際し、洗面具や寝巻きなど身の回り品を購入した費用
・入院中の食事代で病院から提供されたもの以外のもの(外食・出前など)
医療費控除の対象となる出産費用のうち、認められている通院費用とは、「電車賃」や「バス賃」が該当します。
なお、出産で入院する際に、電車やバスで病院へ行くのが困難で、タクシーを利用した場合、この「タクシー代」は医療費控除の対象になります。
参考:国税庁 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例 具体例(2)

【注意点】医療費控除の対象となる分娩費用は「出産育児一時金など」を差し引いた後の金額
こちらの内容をご理解いただくためには、医療費控除の対象となる金額(計算式)を知る必要があります。
この医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式によって求められます。
上記計算式にある「実際に支払った医療費の合計額」は、医療費を自己負担した金額の合計金額です。

「保険金などで補填される金額」は、受け取った生命保険金をはじめ、高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などのことをいいます。
つまり、医療費控除の対象となる分娩費用は、出産育児一時金などを差し引いた後の金額となります。
たとえば、分娩費用が50万円、出産育児一時金が42万円だったとき、医療費控除の対象となる分娩費用は「8万円(50万円-42万円)」といったイメージです。

計算式の注意点(10万円)について
計算式の注意点について、人によっては、必ずしも10万円になるとは限りません。
具体的には、「その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額」となります。
これだけでは全くわからないと思うため、以下、2つの例で自分はどちらにあてはまるか確認してみてください。
収入が給与所得のみの人 
収入が給与所得のみ人は、勤務先から交付された源泉徴収票を確認します。
赤枠で囲まれた金額が200万円未満の人は、10万円を差し引くのではなく、この金額の5%を差し引きます。
たとえば、赤枠で囲まれた金額が100万円だった人は、差し引かれる金額は10万円ではなく5万円(100万円×5%)です。
確定申告をしている人
確定申告をして確定申告書がある人の場合、上記赤枠で囲まれている金額が200万円超えなのか200万円未満なのかで判断します。
医療費控除における出産手当金の取り扱いについて
出産した女性の中には、産前産後休暇を取得したことによって健康保険から出産手当金の支給を受ける人もおられます。
この出産手当金と医療費控除の関係について、国税庁は質疑応答事例で以下のように解説しています。
【照会要旨】
出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金は、欠勤による給与等の減額を補填するために給付されるものですので、医療費を補填するための保険金等には当たらないと考えますがどうでしょうか。
【回答要旨】
照会の出産手当金は、医療費を補填するための保険金等には当たりません。
医療費控除額を計算する場合、医療費の補填に充てられる保険金や損害賠償金があるときは、その金額を支払った医療費の金額から差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、次のようなものは、この医療費を補填する保険金等には当たりません(所得税基本通達73-9)。
出典:国税庁 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金より引用
前項で紹介しましたように、出産育児一時金は、医療費控除の「保険金などで補填される金額」にあてはまりました。
しかし、出産手当金は、医療費を補填するための保険金などではないと解説しています。

【医療費控除の関連記事も紹介】今回の「FP相談対応事例」を通じて伝えたいこと
本ブログの冒頭で、今回の内容は、これから出産予定の人、今後出産する予定がある人、すでに出産を終えて「5年間」が経過していない人にとっては役立つ内容だとお伝えしております。
ここだけを見ますと、なぜ、すでに出産を終えて「5年間」経過していない人が役立つのか?疑問に思う人もいるでしょう。
この理由として、所得税法上、過去5年に遡って還付申告が行えることになっているからです。
つまり、本来ならば医療費控除の適用を受け、節税できる人が医療費控除を受けていなかった場合、納めすぎている税金があることを意味します。
これは、世帯全体にとって多少なりともロスであることは言うまでもありません。
このような理由から、今回のブログ内容は、これから出産予定の人、今後出産する予定がある人、すでに出産を終えて「5年間」が経過していない人にとっては役立つ内容だと思うわけです。
なお、医療費控除にかかる関連記事は、以下から合わせてご確認いただくことをおすすめします。
最後に、納めすぎた所得税の還付を受けるための手続きとして、還付申告と更正の請求について、当事務所で過去に公開した記事があります。
どのような制度でどのような手続きなのか気になる人は、以下、こちらも合わせて読み進めてみるのもよいと思います。
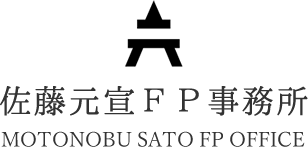





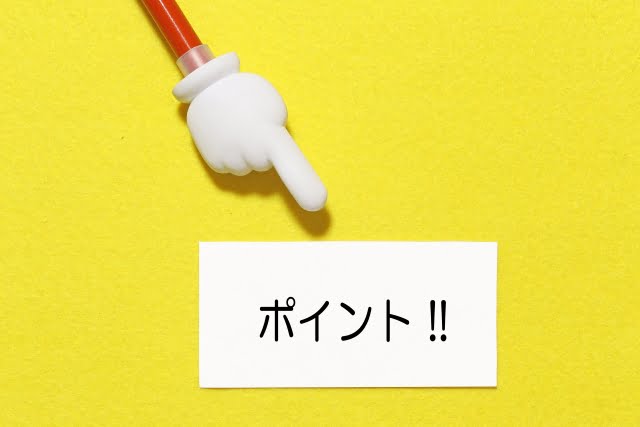
.jpg)


の注意点とポイントを独立系ファイナンシャルプランナー(FP)がわかりやすく解説します.jpg)